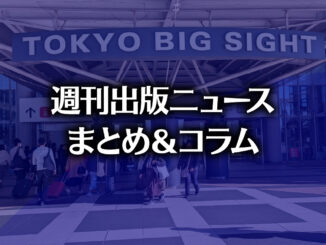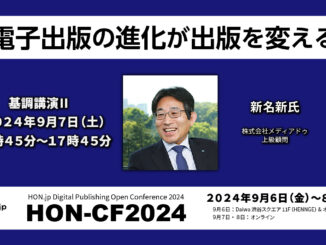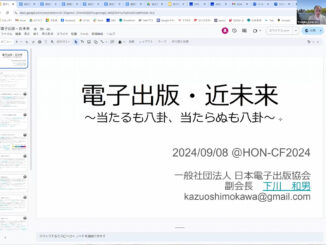《この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です(1分600字計算)》
HON.jpが9月7日に開催したオープンカンファレンス「HON-CF2024」の基調講演Ⅱ「電子出版の進化が出版を変える」の様子を、小桜店子氏にレポートいただきました。
【目次】
出版業界はどうなっていくのか
基調講演は、株式会社メディアドゥ上級顧問の新名新氏が行った。演題は「電子出版の進化が出版を変える」で、副題は「産業としての出版は継続可能なのか……」。44年以上にわたり編集者および経営者として出版業界に携わってきた経験を基に、産業としての出版に焦点を当てて語った。
新名氏は1954年生まれで、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズの1年先輩にあたる。個人向けのコンピューター(現在のPC)に触れたのも同じ時期で、「コンピューターが身近な物になるという時代を生きてきた」と語る。また、出版業界では活版印刷や電算写植、DTP、電子出版など、グーテンベルク以来、世の中に登場してきた出版コンテンツを自ら手がけた経験を持つ。
社会のDXが進むことで出版市場に与えた影響
まず、社会のデジタル・トランスフォーメーション(DX)が進む中で、これまで出版市場がどのように変化してきたのか振り返っていく。日本の出版売上は右肩上がりで伸びていたが、1996年を境に落ちていく。この理由として新名氏は「インターネットの歴史が大きく関係している」と述べた。

ネットの普及に合わせて出版物の入手経路も変化を遂げている。出版売上に対して、紙の書店は2007年まで63.9%のシェアを占めていたが、2022年には40.3%まで落ちている。「紙の書店の苦境はAmazonのせい?」などと言われることがあるが、Web書店は売上を急増させているわけではなく、2022年におけるシェアも14.2%にとどまる。

紙雑誌や紙コミックといった売れ筋の収益で維持されてきた取次や書店も、売上の減少によって苦境に陥った。これに対して、委託制と再販制を改革し、海外のように紙書籍だけで流通が成立するようにシステムを転換するべきという意見が出ているが、新名氏は、出版業界では「かなり難しい。簡単にはいかないという考えが支配的」だと語る。
それには理由がある。出版社側としては、刷り部数印税で支払っている著者との関係性。あるいは、優れた著作だがすぐには部数が見込めない場合、委託制や再販制がない状況では出版が難しい。また、書店側においても、委託制から移行した場合、店内の出版物を全て買い取る必要があり、それは資本の面から困難だという。
電子コミック市場だけが急成長している

日本の出版市場規模は一般書籍とコミックの売上を合わせた場合、2010年と比較すると2019年以降は増加傾向にある。この傾向はアメリカやドイツと違いはない。しかし、この中身を一般書籍とコミックで分けると大きな違いが出てくる。日本の一般書籍は、2010年から緩やかに右肩下がりで、2023年には82.7%まで市場規模が減少している。一方、コミックの場合は、2019年以降は急激に伸びて2023年には149.4%を達成している。電子コミックのみの市場規模を見ると873.4%になっているという。

電子コミック市場が急成長した2つの理由

2つ目は、新しいタイプの出版社が出現したこと。電子書店が他社のコンテンツを売るだけにとどまらず、自社でオリジナルコンテンツを作っているのだ。メディアドゥにおける電子コミックの取次の売上の内、10%ほどは、こうしたコンテンツが占めているという。「電子書店が出版を行うのは有利」だと新名氏は語る。たとえば、自社の投稿サイトに集まるコンテンツの中から有力な物をマーケティングし、出版社を付けてブラッシュアップし売り出していく。こうした手法は「ホームランは出ないが、二塁、三塁打は次々に出る」手堅いビジネスだという。

これからの出版はWeb/AIの時代
これまでの紙出版の時代においては複製や印刷、物流に費用がかかってきた。出版物の価値を生むのは著者だが、組版や造本をする上で出版社や編集者の存在も欠かせなかったという。これが電子出版の時代に移ると、容易に複製や配布が可能になった。
そのため、どこに・どのように配布するかといった「Make Public」が重要になってきたと新名氏は語る。出版物の価値を生むのは変わらず著者だが、読者もこれに関与するようになる。ここまでは紙出版のアナロジーで考えることができ、IPの活用が紙だけでなくデジタルとの両方で可能になったという。


こうした変化は、これまでの紙出版や電子出版とは非連続のものとなり、新名氏は「既存の出版社はこの非連続の境界を乗り越えることに苦労する」と指摘した。
何があってもおかしくない時代

中長期的には電子出版業界に統合的システムやデータ形式が出現すること。電子書籍は消えて無くならない。これは、電子書店が続く限り店頭に残り続けるという利点でもあるが、配信したり、売上や印税を管理する工数が減らない難点でもある。これを克服するため、業界を横断してメタデータやキャンペーンのデータを扱うフォーマットが統合された形で出てくると新名氏は考える。これに成功すると信頼に足る業界統計が作れる可能性もあるという。
また、単価上昇にも関わらず、紙出版の売上の減少は継続していくこと。書店側からすると現状でも出版物による売上は全体の6割程度で、利益になっていない場合もある。書店はその他の物を売って文化事業である出版物の販売を行っている状況だという。
さらに、出版社側からすると、大手出版社の場合、紙の出版物による売上は4割を切っているところもあり、電子出版やライツビジネスが売上の5割以上を占める。そのため、紙の出版物から利益を上げるものではないという経営判断となり、文化事業として位置付けられる可能性があるという。
間に挟まれている紙の取次も苦しい状況にあり、今までの出版物流のシステムを雑貨や文房具などにも使えるように転換するといった別の道を歩み始めている。この結果、大手出版社ではない、また、コミックを持たない中小の出版社の売上や利益に大きく影響することになるという。
それを踏まえて、長期的には紙、電子を問わず出版業界は再編と垂直統合が進むと新名氏は語る。単独で生き残れない時代がやってくる可能性があるとし、中小出版社が資本力のある大手出版社に吸収される、もしくは1つの大きな集まりを作ることがあるという。新名氏の「何があってもおかしくない。そういう時代に今我々は差し掛かりつつある」という言葉に、刺激を受けた関係者も多いだろう。